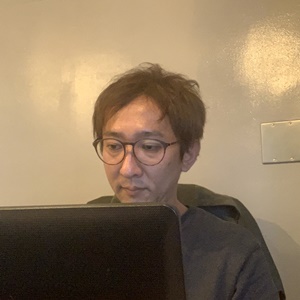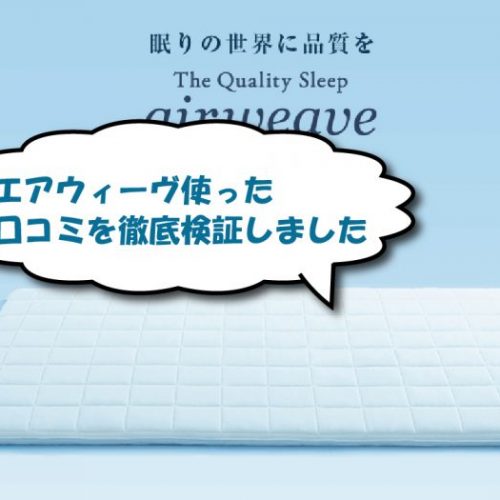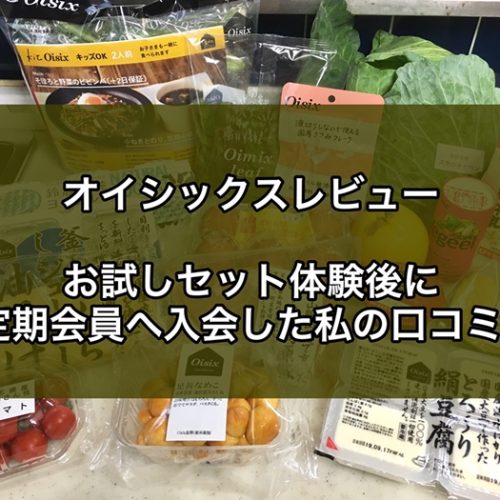ふるさと納税は、寄附することで控除や還付を受けることができます。しかし、メリットばかりで「絶対損しないの?」って気になると思います…。
例えば、納税する側(あなた)にとってふるさと納税は、控除や還付そして返礼品などメリットはたくさんあります。
しかし、メリットが優先されているので、寄附した後にデメリットがあったなんてイヤですよね…。
なので、今回の記事では、ふるさと納税の「メリット」や「デメリット」について嘘偽りなくお話ししていきます!
メリットやデメリットを理解することでポータルサイトの「さとふる」「ふるなび」「ふるさとチョイス」などを利用すると、より便利にふるさと納税を行うことも可能ですよ。
また、豆知識として頭の片隅に入れておいてほしい自治体側のメリットやデメリットについてもご紹介します。これからふるさと納税をする人の参考になれば幸いです!
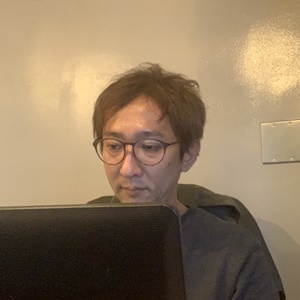
もくじ
ふるさと納税は「納税者」や「自治体」ともにメリットとデメリットがあるの?
| 詳細 | 重要度 | |
|---|---|---|
| 1、納税者のデメリット | 納税者が知らないと損するふるさと納税のデメリットを理解する。 |  5.0 5.0 |
| 2、納税者のメリット | 返礼品・控除・還付などお得なふるさと納税はメリットが多い! |  4.0 4.0 |
| 3、自治体のデメリット | 自治体のデメリットは、収入が他の地域に流れることがある。 |  3.0 3.0 |
| 4、自治体のメリット | 自治体のメリットは、収入が増え地域の活性化を図ることができる! |  2.0 2.0 |
※1~4番の各メリットとデメリットをタップしてもらうと詳しく解説したところに移動します。
ふるさと納税は「控除・還付・返礼品」を受けることができる制度なのでお得感があります!
例えば、控除対象の上限金額内で寄附を行うと、所得税や住民税が控除(還付)されます!さらに、寄附してもらった感謝の気持ちを込めて返礼品も届きます。
これだけ聞くとメリットしかないのでは?と思ってしまいます。
しかし、ふるさと納税をすることで税金を減らすことができるのですが、キャッシュバックと違うところを理解しないといけません…。
なぜなら、あなたが納めている税金に対しての控除額になるので「納税額が0円の人」や「非常に少ない税金」などの場合は還ってきません。
なので、どんな人でもふるさと納税をしたからといって「控除・還付」があるわけではないので注意しましょう!
そして、寄附側だけではなく、自治体側にも「ふるさと納税」のメリット・デメリットがあります。自治体についてのメリットやデメリットを知ると、ふるさと納税の仕組みについても理解しやすいです。なので、どちらもしっかりと見て頂けると幸いです。
ということで、下記からは、より詳しく”ふるさと納税”の「寄附側」「自治体側」のメリットやデメリットを見ていきましょう!
【納税者側】ふるさと納税で注意してほしい5つのデメリットを解説!
| デメリット | 詳細 | 注意度 |
|---|---|---|
| 1、控除を受ける手続き | 控除や還付を受けるには手続きする必要がある。 |  5.0 5.0 |
| 2、限度額の計算が必要 | 寄附する年の確定所得が不明なためある程度の計算が必要です。 |  4.0 4.0 |
| 3、返礼品がない場合もある | 返礼品は全ての自治体で用意されていない。 |  3.0 3.0 |
| 4、返礼品の還元率が減少 | 高価な返礼品に対して自粛要請があり減少している。 |  3.0 3.0 |
| 5、所得によっては控除されない | 限度額以上の寄附をしたら超えた分の金額は控除されない。 |  2.0 2.0 |
※1~5のデメリットをタップしてもらうと詳細に移動します。
デメリットには「控除の手続き」「限度額の計算」「返礼品がない」「還元率が減少」「控除されない」というデメリットがありました。ということで、下記から各項目について詳しく見ていきましょう。
ふるさと納税の確定申告やワンストップ特例制度どちらも面倒なデメリットがあること!

ふるさと納税は寄付することで、控除を受け取ることができるのがメリットでもありデメリットになります。
これは、控除を受けるためには、どれだけ寄付したのかを申告する必要があります。その中には「確定申告の人」「ワンストップ特例制度の人」と2種類があります。
確定申告の人でもワンストップ特例制度の人でも、それぞれ手続きが必要なので、忘れていると控除を受け取ることができないので注意しましょう!
また、ワンストップ特例制度で手続きする場合も、多くて5カ所の自治体に書類を提出しないといけない手間があるのでデメリットですね。
なので、確定申告・ワンストップ特例制度どちらを利用しても手間がかかるデメリットはあります。制度について理解しておかないと控除を受けられないデメリットがあるので注意しましょう。
ふるさと納税の申告方法については「【図解あり】ふるさと納税の仕組みをわかりやすく解説!控除や還付とは?」を参考にしてみてくださいね。
ふるさと納税は上限金額を予想(計算)するのがデメリットであること!

ふるさと納税で実質負担額2,000円以内にするには、所得によって上限金額がある仕組みになっています。
例えば、ふるさと納税をしようと思っても、その年の所得は確定していなので、予想で寄附するしかありません。なので、予想収入から上限金額を判断するしかないところがデメリットになってしまいます。
そこで、利用してほしいのが、ふるさと納税ポータルサイトのシミュレーションです。これは、多くのポータルサイトで利用できるサービスなので、簡単に控除上限金額を調べることができます。
シミュレーションを利用することで目安の上限金額を調べることができるので、ぜひ利用してみてくださいね!
ふるさと納税で「返礼品が届かない」「希望品と違う」というデメリットもあること!

ふるさと納税は、各自治体が絶対に返礼品を用意しないといけない仕組みはないです…。
例えば、自治体を調べず購入して「何も送られてこない…」ということもあるので注意しましょう。また、この返礼品ですが、先着順で募集している自治体もあります。
例えば、応募が多い返礼品がほしくて、ふるさと納税をしようと寄附をします。しかし、先着順のため、寄附する前に品切れになると、違う商品を選ばないといけません…。
そうなると、せっかく欲しかった商品が貰えず損したという気持ちがデメリットになることもあります。
欲しい返礼品があっても上限数を確認することが必要になるので注意して選びましょう!
なので、ふるさと納税をする場合は、ポータルサイトで寄附したい自治体について詳しく確認して返礼品を貰いましょう!
ふるさと納税の返礼品の還元率が減少中のため少しデメリットになっていること!

ふるさと納税の返礼品ですが、還元率が以前に比べて減少しています…。
これは、2017年4月に総務省が各自治体へ「商品券・家電・装飾品など換金性が高い高価な返礼品」の自粛要請があり還元率が減少しています。
しかし、ふるさと納税は、お礼品として地域の特産品を贈ることで購買を促進して活性化につなげるという理念があるので仕方ありません…。
なので、ほしい返礼品があっても多くの人が集中してしまうので、売り切れてしまうデメリットがあります。
ふるさと納税は所得によって控除されないデメリットがあること!

ふるさと納税は、寄附することで所得税や住民税が控除・還付され減額されるメリットがあります。しかし、支払った税金よりも寄付した金額が多ければ損をしてしまうデメリットがあります。
さらに、ふるさと納税を行う期限は、その年の12月31日までです。なので、年末になるまで収入が予想できない人にとってもデメリットです。
なので、実質負担額を2,000円以内でしたい人は、所得予想や見込みをしっかりと計算してふるさと納税することをおすすめします。
どうしても限度額以内で寄附したい人は、ポータルサイトのシミュレーションを行い20%ほど抑えた金額を寄附するとオーバーしにくいと思います。
ここまで、ふるさと納税のデメリット見てきました。確かに、少し書類を提出する手間であったり、収入を予想して寄附しないと負担額が増えてしまうこともあります。
しかし、ふるさと納税とは地域支援や地域活性化という理念があるので、寄附することはデメリットになりませんね!なので、寄附できる人は、社会貢献として利用してほしい制度だと思います。
次の項目では、ふるさと納税にどんなメリットがあるのかをお教えしていきますね!
【納税者側】ふるさと納税をおすすめする5つのメリットって?
| メリット | 詳細 | お得度 |
|---|---|---|
| 1、年収150万円から寄附できる! | 年収が高い人でないと意味がないと思われがちだが150万円以上から寄附できる! |  5.0 5.0 |
| 2、返礼品が貰える! | 負担額が2,000円で控除・還付・返礼品まで貰える! |  4.0 4.0 |
| 3、税金の控除還付がある! | 実質2,000円の負担額で所得税の還付や住民税の控除がある! |  3.5 3.5 |
| 4、復旧や復興に協力できる! | 被災地など復旧や復興に協力するために寄附できる! |  3.0 3.0 |
| 5、ポイント制の自治体を選べる! | ポイント制は返礼品としてポイント貰い有効期限内に好きな品に交換できる! |  2.5 2.5 |
※1~5のメリットをタップしてもらうと詳細に移動します。
ふるさと納税のメリットには「年収150万円から寄附できる!」「返礼品が貰える!」「控除や還付がある!」「被災地に協力できる!」「ポイント制の返礼品」というメリットがありました。ということで、下記から各項目について詳しく見ていきましょう。
ふるさと納税は年収150万円から節税や返礼品を受けれるメリットがあること!

ふるさと納税は、高所得者が寄附して控除・還付を受けれる制度と思っている人も多いです…。しかし、年収150万円ほどからでもしっかりと節税できるメリットがあります!
この年収150万円でふるさと納税する場合ですが、フリーターで社会保険未加入の人だと目安の上限金額が13,000円ほどです。
なので「年収」「家族構成」「住宅ローン控除」「医療費控除」などによっても異なってきますが、年収が高いほどふるさと納税の恩恵を受けやすくなります。
上限金額が不明だという人は、一度ふるさと納税のポータルサイトでシミュレーション機能を活用して控除上限金額を調べてみましょう!
ふるさと納税をすると実質2,000円の負担金で返礼品が貰えるメリットがあること!

ふるさと納税を行うことで、寄附した自治体から返礼品(お礼の品)として、特産物や名産品を受け取ることができます!
デメリットでもお話ししましたが、実質2,000円にするための上限金額を予想する必要がありますが、控除(還付)と返礼品でお得さもメリットになります!
実質負担額を2,000円にする上限金額は「ふるさと納税は上限額以内であれば実質負担額は2,000円の仕組みでお得!」でご紹介した内容を参考にしてみてくださいね!
ふるさと納税をすることで控除や還付を受けれるメリットがあること!

返礼品が貰えるメリットでもお話ししましたが、ふるさと納税を行うことで「控除・還付」があります。
例えば、家族構成や所得に応じた上限金額までを寄附した場合、2,000円が負担金となり残りを控除や還付で受け取ることが可能です。
さらに、住民税の基準で決められている「保育料」や「高校の授業料」が変わることもあります。
なので、寄附することで税金を安くしてもらい、返礼品(お礼の品)まで貰えるので大きなメリットですね!
ふるさと納税は被災地など復旧や復興の支援するメリットがあること!

ふるさと納税は、被災地などの復旧や復興の支援をしたい人におすすめの寄附金制度です。
各自治体は、寄附されたお金の使い道を開示しているので、自分が選びたい自治体に寄附できるところもメリットですね!
そして、本来の税金は住んでいる自治体になるのですが、支援したい自治体を自分で選べるところが貴重な制度でメリットです。
ふるさと納税のポイント制は有効期限内ならいつでもお礼品に交換できるメリットがあること!
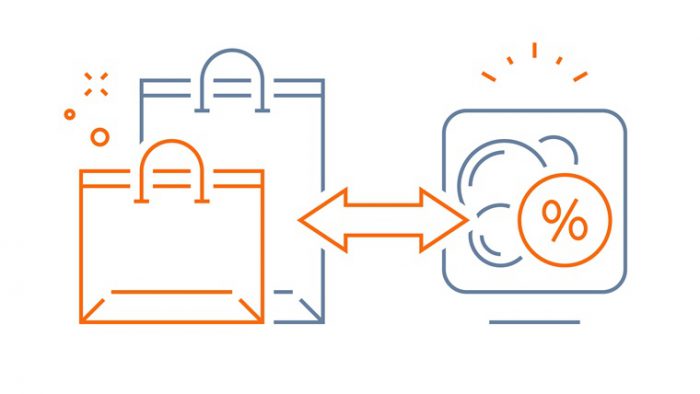
ふるさと納税は、返礼品がすぐ届く自治体と、お礼品への交換ができるポイントを付与してくれる自治体があります。
このポイント制を利用する事で、好きな時にほしい商品と交換できるメリットがあります!
例えば、返礼品を選ばないといけないけど「どれにしようか迷って…」という時間だけが過ぎてしまう人も多いですよね。
その時は、好みの商品がある時に使えるポイント制を扱っている自治体を利用してもいいですね!
ふるさと納税は、年収が少ないからと思い興味が無かった人や、返礼品を選ぶことが大変だった人にも、数多くのメリットがありましたね。
まずは、ふるさと納税ポータルサイトで、あなたの控除上限金額をシミュレーションして、寄附したい自治体を見つけてみましょう!
その時に、ほしい返礼品がない時は、ポイント制を利用できるのかも確認しておくといいですね!
【自治体側】ふるさと納税してもらうメリットやデメリットってあるの?
ここからは、寄附される側である自治体に、ふるさと納税のメリットやデメリットがあるのかを調べてみました。いい事も悪いこともあると思いますが、自治体側を知ることでふるさと納税をする理由を見つけることも可能です!
自治体側のふるさと納税のデメリットって?
- 住民が他地域の自治体に寄付してしまう
- 税収が減少する可能性がある
- ふるさと納税制度に導入する手間が掛かる
- 返礼品とする産物がない
- 支払手段によってはコストが掛かる
ふるさと納税で寄附によって税収が増えるはずの自治体にもデメリットがありました。
しかし「税収が増える=他自治体の税収が増える」ということにもなるので、他の地域に寄附された場合は、税収が減ってしまうデメリットがあります。
なので、住民が他の自治体に寄附してしまうと収入が少なくなってしまいます。また、特産物や名産品がある自治体の場合は、宣伝効果にもなるのでメリットでもあります。
しかし、これといった返礼品がないと寄附してもらう産物を探すところからスタートになるのでデメリットです。
返礼品目当ての人が多ければ多いほど、デメリットになってしまう自治体もあります。
自治体側のふるさと納税のメリットとは?
- 全国から寄附が貰えると収入を確保できる!
- 人気の特産品がある自治体は寄付を集めやすい!
- 優待券などを返礼品として送ると観光誘致しやすい!
- 被災地の復旧や復興に役立てることができる!
- 返礼品による産物の宣伝をPRしやすい!
- 産物がなくても工夫次第で特典品を用意できる!
- 各役所で働く職員のモチベーションが上がる!
ふるさと納税は寄附側にもメリットがたくさんありましたが、自治体側にもメリットがあります。
各自治体では「復旧や復興」「返礼品」「観光誘致」など、ふるさと納税によって地域のPRをしやすいメリットがあります。なので、寄附を集めて収入を増やすしやす特長があります。
そして、寄附のお礼を返礼品として送ることがありますが、特産品をPRしやすいのでメリットとなっている自治体も多いですね!
さらに、返礼品を名産品ではなく、地域で利用できる「割引券」や「優待券」などを発行して、観光誘致することもできます。
なので、寄附側も大きなメリットがたくさんありますが、各自治体にもメリットがあります。お得なふるさと納税を行うことで社会貢献にも繋がるので、利用している人が増えていますね!
楽天のふるさと納税を利用するメリットやデメリットってないの?
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 楽天会員は寄附するのが簡単! | 登録している楽天IDが寄付者になる |
| 楽天市場で買い物をするように寄附できる! | ー |
| 楽天スーパーポイントが「貯まる!」「使える!」 | ー |
| クレジットカードで寄附できる! | ー |
| 返礼品のレビューやランキングがある! | ー |
楽天のふるさと納税のメリットとデメリットを調べてみました。楽天で気になるデメリットは1つだけでした。
まず、デメリットの「登録している楽天IDが寄付者になる」を見ていきましょう。楽天ふるさと納税は、登録している楽天IDで管理されています。この”楽天ID”に注意してほしいです。
例えば、1つの家族で楽天IDを1アカウントしかないとします。また、この楽天IDの名義は専業主婦の奥様です。旦那様の所得控除によってふるさと納税しようと思っていても楽天IDの名義が違うと、奥様が寄附したことになってしまいます。
なので、高額な寄附を行っていても、所得がない専業主婦の場合、控除や還付を受けることができません…。なので、楽天IDの名義をしっかりと確認することが大切です!
そして、楽天利用者なら「登録が簡単」「返礼品を買い物感覚で探せる」「ポイントが貯まる」「クレジットカードで寄附できる」「レビューやランキングの充実」などメリットが多いですね!
ふるさと納税のメリットデメリットでその他のよくあるQ&A一覧
ここからは、ふるさと納税を考えている人で、質問が多かった内容をQ&A形式でお答えしていきます。
ふるさと納税のポイント制のデメリットはないの?
ふるさと納税をサラリーマンが行うメリットってありますか?
ふるさと納税をする法人(企業)ってメリットがあるの?
災害支援のために行うふるさと納税のメリットって?
ふるさと納税のメリットとデメリットまとめ
今回は、ふるさと納税の「メリット」と「デメリット」について調べてみました。
ふるさと納税は、実質2,000円の負担金で返礼品が貰えたり、所得税や住民税の控除を受けることができたり”メリット”が注目される理由もわかりましたね。
しかし、そのメリットだけを考えていると大きな損をすることもあります。例えば、返礼品欲しさに高額な寄附することはいいのですが、上限金額を超えてしまい自己負担額が増えてしまうこともあります。
なので、初めての方でご紹介した「【納税者側】ふるさと納税で注意してほしい5つのデメリットを解説!」を理解しておくと、ふるさと納税を行うメリットが分かりやすいですね!
ふるさと納税は「地域貢献・社会貢献・災害支援など」多くの協力が必要な地域を応援することができる制度ですね!