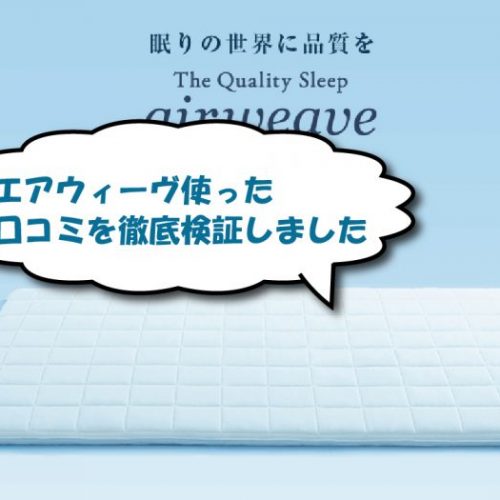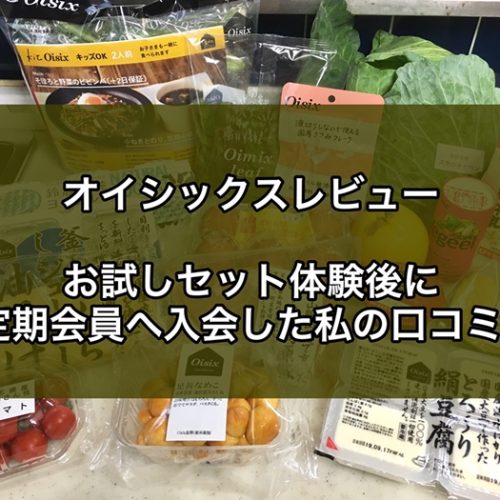生活保護を受けている人が引っ越しをしたい場合、こういった疑問は出てこないでしょうか?
- そもそも引っ越しはできるのか?
- 費用は負担してくれるのか?
生活保護を受けていることで引っ越しの際にいろんな制約があるのでは?と不安に思うかもしれません。
まず先に言ってしまうと、生活保護を受けている方の引っ越しはいろいろと制約がつくものです。
ではどういった制約があるのか?ということで、今回の記事で詳しく解説していきます。内容をぜひチェックしてみてくださいね!

もくじ
そもそも生活保護者でも引っ越しはできるの?

まず最初に結論を言いますと、生活保護を受けている方でも引っ越しはできます。
というのも居住移転の自由は日本国憲法でも保障されているからなんです。
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
参照:日本国憲法22条1項
このように住む場所を選ぶ自由は憲法で保障されているので、生活保護を受けている方も例外なく引っ越しができるということなんですね。
ただし、引っ越しは自由にできるんですが、引っ越し費用についてはまた別の話になってきます。
まず、自己都合で引っ越しをする場合は、引っ越し費用は自己負担になってしまうんです。
それに仮に引っ越し費用を捻出できたとしても、役所から「この人はお金に余裕があるんだな」と目を付けられて、生活保護が打ち切りになる可能性もあります。
結局のところ自己都合での引っ越しはおすすめできないということです。
ですが自己都合ではなく、きちんと理由があって引っ越しをする場合は、引っ越し費用が負担されます。
どういった理由なら引っ越し費用が負担されるのか?ということで、次で紹介していきます。
生活保護者が引っ越し費用を受け取るには理由が必要

生活保護を受けている方が引っ越し費用を受け取るには、以下の16個の理由のうちいずれかに該当する必要があります。
- 入院していた人が退院後に住む場所がない場合
- 家賃が自治体の規定する上限額をオーバーしていて、引っ越しを指導された場合
- 都市計画などによって立ち退きを強制された場合
- 退職によって社宅を出なければならなくなった場合
- 社会福祉施設を退所して住む場所がない場合
- 宿泊提供施設や無料定額宿泊所の利用者が、居宅生活ができると認められた場合
- 会社までの距離が遠く、通勤が困難である場合
- 火災などの災害によって住居が消滅、あるいは居住できなくなった場合
- 老朽や破損で居住できない住居になった場合
- 世帯人員に対して住居があまりに狭い場合
- 病気療養上または身体障害者にとって適さない住居の場合
- 一時的に部屋を借りていた親戚・知人宅から転居する場合
- 家主に退去を求められたり、借家契約の更新の拒絶や解約があった場合
- 離婚によって新たな住居が必要になった場合
- 高齢者や身体障害者が日常的に介護を受けるために、扶養義務者の近隣に引っ越す場合
- グループホームや老人ホームなどに入居する必要がある場合
これらのうち1つでも満たしていれば引っ越し費用が負担されます。
ただ、レアな条件も多いのでなかなか該当するものが見つからないかもしれません。
ということでここからは、16個の条件のうち比較的認められるケースの多い次の2つの条件について紹介していきます。
- 家賃が自治体の規定する上限額をオーバーしていて、引っ越しを指導された場合
- 病気療養上または身体障害者にとって適さない住居の場合
では1つずつ見ていきましょう。
家賃が自治体の規定する上限額をオーバーしていて、引っ越しを指導された場合
各自治体で生活保護の際に負担してくれる家賃の上限額は決まっています。
しかし、その上限額以上の家賃の部屋に住んでいる場合は、ケースワーカーから引っ越しを指導される場合があります。
ケースワーカーの指導が入って引っ越しをする場合は自己都合にはなりません。なので引っ越し費用が負担されるということですね。
ちなみに引っ越しを指導されたのに拒否し続けたら、最終的には生活保護自体が打ち切りになってしまう可能性があります。
生活保護の打ち切りだけは避けたいので、必ずケースワーカーの指示に従うようにしてください。
病気療養上または身体障害者にとって適さない住居の場合
このケースだと例えば次のような人が当てはまります。
- うつ病の人 … 住居の騒音がひどく、うつ病が悪化しそうな場合
- 身体障害者の人 … 住居がバリアフリーではないため住みにくい場合
こういった事情のある人は引っ越しの際の費用が負担されます。
ただし、騒音の感じ方については人それぞれです。仮に本人がひどい騒音だと感じていても、一般的には騒音ではないと判断される可能性もあります。
そうなると引っ越し費用の負担条件を満たさなくなってしまうので注意が必要です。
なのでまずはケースワーカーに相談してみるのがいいでしょう。
生活保護者は引っ越し費用がどこまで負担される?
仮に引っ越し費用の負担が認められたとしても、「引っ越し費用ってどこまで負担されるの?」と疑問に思いますよね。
引っ越し費用には様々な費用がありますので、ここではどの費用が負担されるのかをまとめてみました。
| 費用 | 内容 | 負担の可否 | 負担額 |
|---|---|---|---|
| 引っ越し代 | 引っ越し業者に払う費用 |  |
全額 |
| 敷金 | 部屋の退去時の修繕費に充てるために事前に預けるお金 |  |
他の費用と合算して住宅扶助上限額×3.9まで負担 |
| 前家賃 | 翌月分の家賃を契約時に前払いする |  |
|
| 礼金 | 大家さんに払うお礼のお金 |  |
|
| 仲介手数料 | 不動産会社に払う仲介手数料 |  |
|
| 保証料 | 連帯保証人を立てられない場合に払う料金 |  |
|
| 火災保険料 | 火災や水漏れなどに備えるための保険料 |  |
|
| 新居の鍵交換代 | 新居の鍵を取り換える際の費用 |  |
|
| クリーニング代 | 前に住んでた部屋のクリーニング代 |  |
- |
| 管理費・共益費 | 玄関や階段などの物件の共有部分を維持、管理するための費用 |  |
- |
| 家具什器(じゅうき)費 | 生活に必要な家具や家電の購入費 |  |
|
ではこれらの費用について詳しく見ていきましょう。
引っ越し費用は全額負担される

まず最初に引っ越し費用についてですが、こちらは全額負担されます。
ただし、引っ越し費用は自治体が負担するわけですから、自治体としても費用はできるだけ安い方がいいはずです。
なので複数の業者に見積もりを取るように、ケースワーカーから言われると思います。
そんな時に便利なのが引っ越し業者の一括見積もりサービス。複数の引っ越し業者から安い業者を選ぶことができます。
ちなみに当サイトではSUUMOの一括見積もりサービスをおすすめしています。全国の引っ越し業者と提携していますので、安い引っ越し業者が簡単に見つかりますよ。
敷金等は確実に負担されるものと自治体によって負担の可否が変わるものがある

生活保護を受けている方は敷金等も引っ越しの際に費用を負担してもらえます。
ただし、敷金等には様々な項目が含まれており、確実に費用を負担してくれるものや各自治体で負担の可否が変わるものなど様々です。ここではそれぞれの項目を分類してみました。
- 確実に負担されるもの … 敷金、前家賃、保証料(連帯保証人を立てられない場合)、火災保険料
- 自治体によって負担の可否が変わるもの … 礼金、仲介手数料、新居の鍵交換代
このように自治体によっては負担されない可能性のある費用もありますので、まずはケースワーカーに相談してみるといいでしょう。
ちなみにこれら敷金等は負担される金額の上限が次のように決まっています。
- 住宅扶助上限額×3.9
住宅扶助上限額は各自治体で異なります。
例えば住宅扶助上限額が50,000円なら、50,000円×3.9=195,000円まで負担されるということです。つまり、この負担額の中に敷金等の合計金額が収まればいいということですね。
ちなみに県外や市外、区外などへの引っ越しで管轄する自治体が変わる場合、住宅扶助上限額は金額が高い方の自治体が優先されます。例えばこんな感じです。
- 現在は7万円が住宅扶助の上限で新居では10万円が上限 ⇒ 10万円が適用
- 現在は7万円が住宅扶助の上限で新居では5万円が上限 ⇒ 7万円が適用
このように上限額の高い方が適用され、この上限額をもとに敷金等の負担額が決まります。
敷金0円の物件には要注意!

物件を探す際には敷金0円の物件には注意してください。というのも敷金0円の物件は退去時にクリーニング代を支払う必要があるから。
敷金は新しい物件の入居時に支払うお金ですが、この敷金は部屋の退去時のクリーニング代として使われます。
つまり敷金が0円ということは、部屋の退去時にクリーニング代に充てるお金がないということです。
そして、自治体ではクリーニング代を負担してくれませんので、クリーニング代は自分で払わなければなりません。
生活保護を受けている人が自腹でクリーニング代を払うのは、さすがに大変だと思います。なので敷金0円の物件は選ばない方がいいでしょう。
敷金は住宅扶助できちんと負担されますので、敷金の必要な物件を選ぶことをおすすめします。
引っ越しの際は家具什器(じゅうき)費も負担される

家具什器費とは生活に必要な家具や家電を買うための費用のことです。
生活保護を受けている人は最低限度の生活をするために、家具什器費を使って最低限必要な家具や家電を買うことができます。支給額についてはこちら。
| 項目 | 支給額上限 | やむを得ない事情で支給額をオーバーする場合に認められる支給額の上限 |
|---|---|---|
| 炊事用具、食器など | 29,100円 | 46,400円 |
| 暖房器具 | 20,000円 | 50,000円 |
| 冷房器具 | 50,000円 | - |
ただし、何でもかんでも買っていいわけではありません。
例えばテレビやスマホなどは最低限度の生活には必要ありませんので、家具什器費の対象外となります。
また、家具什器費の支給対象であっても、次のような場合でないと購入もできません。
- これまで使っていた家具や家電が使えなくなってしまった場合
- 必要な家具や家電をそもそも持っていない場合
これまで使っていた家具や家電がまだ使えるのに、新しい家具や家電に買い替えるなんてことはできないということですね。
他にも、どういった家具や家電が費用の支給対象かは、各自治体や担当するケースワーカーでも変わってくるという注意点もあります。
なので、まずはケースワーカーに相談して、費用の支給対象を確認してみるのがいいでしょう。
引っ越し時に費用が支給されない項目について

引っ越し時に費用が支給されないものも存在します。例えばこちら。
- 部屋のクリーニング代
- 管理費・共益費(玄関や階段などの物件の共有部分を維持、管理するための費用)
部屋を出る際にかかるクリーニング代は新居への引っ越しには直接的に関係ありません。なのでクリーニング代は支給されないということなんです。
また、生活保護では家賃が負担されるんですが、管理費・共益費は家賃には含まれません。なので管理費・共益費についても受け取れないということなんですね。
生活保護者が引っ越しをする際の具体的な流れ
ここからは生活保護を受けている人が引っ越しをする際の具体的な流れを解説していきます。
- 役所に引っ越しの許可を得る
- 物件を探す
- 決まった物件をケースワーカーに報告する
- 不動産会社で物件の契約をする
- 引っ越し業者を選ぶ
- 物件の契約書類と引っ越しの見積もり書を持ってケースワーカーに相談しに行く
- 引っ越しをする
- 県外や市外、区外などへ引っ越す場合は生活保護を再申請する
- 家具什器(じゅうき)を揃える
これら具体的な流れについて解説していきます。
役所に引っ越しの許可を得る

まず最初に役所に行って引っ越しの許可を得ます。
引っ越し自体は自由にできますが、引っ越し費用は「16の条件」のうちいずれかを満たさないと支給されないという話でしたね。
なので、まずは役所に行って引っ越しの許可をもらい、引っ越し費用が支給してもらえることを確認しましょう。
また、引っ越し費用はどこまで負担されるかも確認しておくべきですね。礼金や鍵の交換代も負担されるのかも確認しておきたいところです。
その場合は役所同士がやり取りをしてくれ、必要な書類も送ってくれます。あとは役所の指示に従って手続きを進めてください。
また、別の市町村に引っ越す場合は、引っ越し先の自治体から生活保護の扶助がどれくらい受けられるのかも確認しておくといいでしょう。扶助の金額によって選ぶ物件も変わってくるので。
引っ越し先の物件を探す

役所から引っ越しの許可が下りたら、次は引っ越し先の物件を探します。
引っ越しの際には敷金等(敷金、礼金、前家賃、仲介手数料、保証料、火災保険料など)の費用が負担されますが、負担額の上限は「住宅扶助上限×3.9」までです。
なので負担額の上限に収まるように物件を探していきましょう。
ちなみに先ほども話したように、管理費・共益費、退去時のクリーニング代などは、費用負担の対象外です。
これらの費用は自腹となりますので、できるだけこれらの費用が安い物件を選ぶことをおすすめします。
引っ越し先物件をケースワーカーに報告する

引っ越し先の物件を契約する前に、まずはケースワーカーに報告をして許可をもらいます。
住宅扶助の上限額を超えた物件を選んだ場合は、当然ながら許可は下りません。
贅沢な物件を選ぶなんてことはないと思いますが、念のため物件選びに注意して、ケースワーカーに許可が得られるようにしてください。
不動産会社で物件の契約をする

ケースワーカーから許可が下りたら、不動産会社で物件の契約をします。この時、以下のものを保管しておくようにしましょう。
- 住宅契約書
- 契約時の領収書
これらはケースワーカーに提出するために保管しておく必要があります。
引っ越し費用を負担してもらうのに大切な書類ですので、失くさずに保管しておいてください。
引っ越し業者を選ぶ

次に引っ越し業者を選びます。
引っ越し料金は全額負担してくれますが、役所としては出来るだけ安い業者に引っ越しを依頼してほしいと考えています。
そして、ケースワーカーに相談した際には、複数の業者に見積もりを依頼するように指導されるはずです。
なので複数の引っ越し業者に見積もりをお願いして、安い業者に引っ越しをお願いするようにしましょう。
ちなみに見積もりをお願いする際は、一括見積もりサービスを利用するのが便利です。
当サイトではSUUMOの一括見積もりサービスをおすすめしています。SUUMOは全国の引っ越し業者と提携していますので、お得な引っ越し業者を選ぶことができますよ。
物件の契約書類と引っ越しの見積もり書を持ってケースワーカーに相談しに行く

ここまでで物件と引っ越し業者が決まりましたので、引っ越し前の最終確認としてケースワーカーに相談しに行きます。
相談に行く際は以下のものを持って相談に行きましょう。
- 住宅契約書
- 契約時の領収書
- 引っ越し業者の見積もり書
ケースワーカーが確認をして許可が下りれば、ようやく引っ越しができるようになります。
引っ越しをする

役所から引っ越しの許可が下りたら、あとは引っ越し業者に依頼した日程で引っ越しをします。
事前に余裕を持って荷造りをしておけば、あとは引っ越し業者がすべてやってくれるので、スムーズに引っ越しが完了します。
また、引っ越しの際には電気、ガス、水道の手続きも必要です。引っ越し日に合わせて電気、ガス、水道の使用停止や新居での使用開始の手続きを済ませておきましょう。
県外や市外、区外などへ引っ越す場合は生活保護を再申請する

県外や市外、区外などへ引っ越す場合は、生活保護を担当する自治体が変わるので、生活保護の再申請が必要になります。※同じ市や区に引っ越す場合は不要。
なので引っ越し後には生活保護の再申請を忘れずにしましょう。
ちなみにこの時注意したいのが再申請をする日にち。引っ越し前に住んでいた地域での生活保護が廃止される当日に生活保護の再申請をするようにしましょう。
理由としてはこちら。
- 再申請が1日でも遅れると国民健康保険への加入が必要になり、手続きが面倒だから
- 国民健康保険の加入によって負担が増えてしまうから
これらの理由があるので、前に住んでいた地域での生活保護が廃止される当日に生活保護の再申請をするようにしてください。
ちなみに生活保護の再申請後には審査があります。審査結果が出るまでは2週間以上かかり、その間は手持ちのお金で乗り切る必要があるので注意してください。
生活保護の審査に通れば、審査に通るまでの期間の生活保護費は支給されますので、その点はご安心を。
家具什器(じゅうき)を揃える

先ほども話しましたが、生活保護を受けている方は家具什器費を負担してもらえます。家具什器費とは生活するために最低限必要な家具や家電を揃えるための費用です。
家具什器費がどれくらい負担されるのかをあらためて載せておきますね。
| 項目 | 支給額上限 | やむを得ない事情で支給額をオーバーする場合に認められる支給額の上限 |
|---|---|---|
| 炊事用具、食器など | 29,100円 | 46,400円 |
| 暖房器具 | 20,000円 | 50,000円 |
| 冷房器具 | 50,000円 | - |
これらの支給額の範囲の中で必要な物を揃えてみてください。
ただし、費用が負担されるのは最低限の生活のために必要な物だけです。
生活保護者の引っ越しに関するその他のQ&A
生活保護者だと不動産の仲介を拒否されることもあるの?
ただし、個人経営の不動産会社では仲介を拒否される可能性もあります。
逆に大手の不動産会社なら「生活保護でも入居可」といった物件も用意されていますので、心配なら大手の不動産会社で物件を探すといいかもしれません。
生活保護者だと引っ越し業者に拒否されることがあるの?
というのも生活保護者の引っ越し費用は行政が負担してくれるということを、引っ越し業者もわかっているからです。
生活保護者だからと言って引越し業者に拒否されることはないので安心してください。
引っ越し先の物件を探す際に保証人がいない場合は?
保証料は自治体で負担してくれる可能性もあるので、まずはケースワーカーに相談してみてください。
また、不動産会社では「生活保護受給者」「保証人なし」といった条件で物件探しもできますので、まずは不動産会社で相談してみるといいでしょう。
生活保護者の引っ越し情報まとめ
今回は生活保護を受けている方の引っ越しについての情報を話してきました。最後に今回の内容をまとめます。
- 生活保護者でも引っ越しは自由にできる。
- ただし自己都合の引っ越しは費用が負担されない。
- 引っ越し費用を負担してもらうには条件を満たす必要がある。
- 敷金等や家具什器(じゅうき)費なども負担される。
- 自治体によって費用負担の可否が変わる項目もあるので、必ずケースワーカーに相談する。
結論としては、生活保護を受けている方でも引っ越しは可能で、条件を満たせば引っ越し費用を負担してもらうことも可能ということです。
ただ、実際に引っ越し費用を負担してくれるかどうかは、各自治体や担当するケースワーカーの判断によります。
ということでまずはケースワーカーに引っ越しの相談をしに行ってみてくださいね。
以上、生活保護者の引っ越し情報まとめでした。